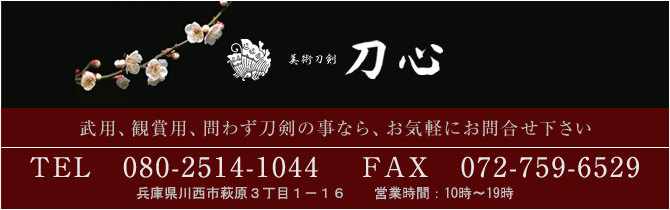脇指 783 脇指 783 |
 |
無銘(下原) |
 |
- Mumei(Shitahara) - |
|
|
|
| 刃長 |
一尺五寸一分四厘八毛強 / 45.9 cm |
反り |
五分六厘弱 / 1.7 cm |
| 元幅 |
31.8 mm |
元重 |
7.2 mm |
| 先幅 |
物打28.6 mm |
先重 |
物打5.4 mm |
| 目釘穴 |
1個 |
時代 |
室町後期
The latter period of Muromachi era |
| 鑑定書 |
保存刀剣鑑定書 |
登録 |
平成21年8月12日 広島県登録 |
| 附属 |
・銀はばき
・白鞘 |
価格 |
176,000 円(税込)
 |
|
 |
|
武州下原刀は、武蔵国弾軍の恩方村、横川村、慈根寺村(元八王子村)等に散財した山本姓を名乗る一族の刀工群が製作した刀剣類の総称で、現在の東京都八王子市で活躍しました。
この地は管領山内上杉領で、上杉家の老職(武蔵守護代)の滝山城主大石道俊、そして、小田原北条氏の関東制圧後は三代氏康の次男八王子城主北条氏照の庇護を受け、二代周重は北条氏康から”康”の一字を賜り「康重」と改名。康重の弟は、北条氏照から”照”の一字を貰い{照重}と改名。その後、徳川家からも厚く庇護され、その御用を勤めました。中には水戸光圀から一字を賜った刀工も居ります。
作刀上では室町時代末期より、安土桃山、江戸時代を通して、周重・康重・照重・廣重・正重・宗國、安國等の刀工を生み、代々下原鍛冶の伝統を受け継ぎ、江戸初期からは新刀伝をとり入れた作刀も多く見られ、下原鍛冶は十家に及び「下原十家」と言われました。江戸中期以降になると衰退するも、幕末まで続く武州唯一の刀工群です。
この脇指は身幅広目で反り深く、棟を三ツ棟。地鉄は小板目よく練れるも処々に大肌が立ち、刃文は小沸本位で匂口明るく、直刃調に互ノ目足を盛んに入れ、鋩子は直ぐに先丸く返り、指裏の返りには蛇の目刃を交えている。
前所有者がはばきを替えたようで、白鞘と茎の目釘孔にズレがあります。新たにはばきを新調されるか、或いははばきの台尻を削って短くされるか、また或いは白鞘の目釘孔を広げる工作をお勧め致します。
裸身重量466グラム。
※委託品
各種クレジットカード、セディナショッピングローンによる分割購入も承っております。お気軽にお申し付け下さい。
|
|

|