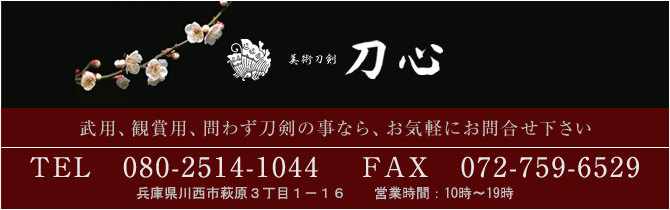刀 1721 刀 1721 |
 |
無銘(新々刀相州綱廣) |
 |
- Mumei(Soshu Tsunahiro) - |
|
|
|
| 刃長 |
二尺三寸一厘九毛強 / 69.75 cm |
反り |
五分二厘八毛 / 1.6 cm |
| 元幅 |
31.6 mm |
元重 |
7.8 mm |
| 先幅 |
物打25.7 mm 横手位置22.4 mm |
先重 |
物打6.6 mm 松葉先6.0 mm |
| 目釘穴 |
1個 |
時代 |
江戸後期
The latter period of Edo era |
| 鑑定書 |
保存刀剣鑑定書 |
登録 |
昭和38年3月22日 島根県登録 |
| 附属 |
・真鍮地銀鍍金はばき
・海軍太刀型軍刀拵(藍鮫研出鞘) |
価格 |
800,000 円(税込)
 |
|
 |
|
相州住綱廣は室町後期から江戸末期まで連綿と続いた相州鍛冶です。
初代は山村姓で、初銘を正廣と切りましたが、その後小田原の北條氏綱に召出され、「綱」の一字を賜り綱廣と改銘したと言われています。
綱廣の代別は難しいと言われていますが、藤代刀工辞典では初代が天文、二代が永禄、三代が文禄とされており、山村家系図および古文書によると天文七年(1538)から天文十年(1541)の間に初二代の代替があったとされています。
三代綱廣は山村宗右衛門と称し、鎌倉扇ケ谷に住しましたが、後に津軽藩主の招きによりその地へ移り、大小300振を鍛刀し、慶長11年(1606)に帰国したとあり、その作品の銘には「津軽主為信相州綱廣
慶長十乙巳八月吉日 三百腰之内」「津軽主為信相州綱廣呼下作之 慶長十乙巳八月吉日」等が遺されており、綱廣の名跡は江戸末期迄連綿と続き栄えました。
この刀は元先の幅差頃好く開いて切先延び、地鉄は杢目がよく錬れて肌立ち精美。刃文は互ノ目と湾れを基調に飛焼盛んに焼いて皆焼を成し、丁字刃交じり、足、葉入り、鋩子は小さく乱れ込んで先掃き掛け、沸筋食い下げて返る。
写真では刃中に鍛え疵があるように見えますが、これらは錆であり、鍛錬疵ではありません。総じて無疵無欠点。銘を切らなかったことが訝しい程の出来良い作品です。
附属の拵は完全なうぶで、柄や鯉口内部に『海中』と鉛筆書きされていることから、とある海軍中佐による別注であることが窺い知れます。
柄にがたつき無し。鐔鳴りほぼ無し。
裸身重量842グラム。 拵に納めて鞘を払った重量1,223グラム。
※保存刀剣鑑定書は日本美術刀剣保存協会から届き次第お届け致します。
|
|

|